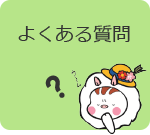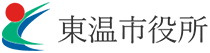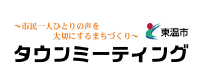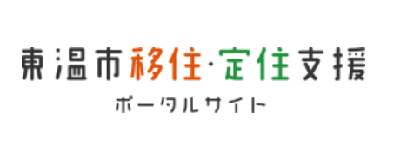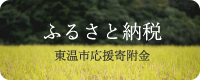本文
家庭の備蓄品
「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」が最終報告を公表しました。
その中で、国の防災基本計画で「3日分」であった、水や食料の家庭備蓄を「1週間分」とすることを促しています。
2011年3月11日に発生した東日本大震災では、食品や飲料水の継続的な救援が行なわれましたが、被災地では食料を含む物資の著しい不足が4月に入るまで続きました。
原因等は?
- 災害時応援協定を結んでいたスーパー・コンビニエンスストア・企業等が被災し、道路網も寸断され、流通備蓄が機能しなかった。
- 救援物資輸送は、トラック輸送が大部分を占めたが緊急交通路の確保等の緊急輸送体制が混乱した。
- 車両や燃料(ガソリン)不足により輸送能力が低下した。
- 地方自治体の施設被災により情報収集・伝達機能が喪失し、状況把握が不可能となった。
等
飲料水や食料が被災者に行き渡らないという問題は、発生が差し迫っているとされる「南海トラフ巨大地震」では、東日本大震災以上であると予想されます。
| 水 | 1人1日当たり3リットル。4人家族の場合、2リットルペットボトルで42本 |
|---|---|
| 米 | 1人1日当たり3合(約450g)。4人家族の場合、約13kg |
| 食材 | 根野菜や乾物、レトルト食品や缶詰など種類を豊富に。 |
| 燃料 |
カセットコンロのガス、250g缶1本は燃焼1時間として1日2本以上。1週間で14本 |
| 電池 | 携帯電話の充電やライト用に。 |
| トイレ | 尿や便を固める凝固剤や袋など。排せつ回数は1人1日4から8回として計算する。 |
| できれば! |
|
循環備蓄のおすすめ!
1.普段食べているものを備蓄にしてみましょう!
たとえば、お米を買ってきたら米びつに入れて保管しますが、もう一袋余分に買ってストックしておけばその分が備蓄品となります。米びつの中の米がなくなったらストックしていたお米を米びつに入れて一袋買っておけば、賞味期限を気にせずに備蓄できるということです。
食料品の備蓄というと、まずはカンパンやアルファ米など長期保存が可能なものをイメージすると思いますが、普段食べているものを少々多く購入しておくことが、そのまま備蓄になっているということです!
2.賞味期限を確認しましょう!
食品によって賞味期限は様々です。
せっかく備蓄しても、いざ食べようとする時、賞味期限が切れていたらもったいないですよね。
- インスタントラーメンは、大体数ヶ月
- チョコレート類は、約1年ほど持つものも
- 乾燥パスタは、数年間保存できます
※種類によって違いますのでこまめに確認しましょう!
3.普段から備蓄品を食べるようにしてみましょう!
大雨などの悪天候のとき外出するとおもわぬ事故に遭うことも。
そんな時には、外出を控えて、食事は備蓄品を食べてみてはいかがでしょうか?
普段から備蓄品を食べてドンドン消費して、なくなる前に買い足していけばよいのです。
飲料水も同じように循環備蓄して古くなる前に次々に飲んでいきましょう!
長期保存できる食品と合わせて上手に備蓄すればさらに安心です。
ぜひ循環備蓄を試してみてください!